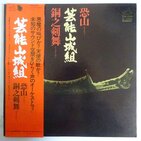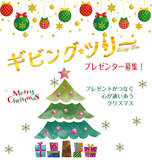|
僕の車のナンバーは「496」です。何の変哲も無い数字に見えますが、実はリクエストして手に入れた拘りのナンバーなのです。
自分自身を除いた約数を足すとその数自身になる…という性質をもった数を「完全数」といいます。 1番小さい完全数は6。その約数は1, 2, 3, 6で1+2+3=6となります。2番目の完全数28。その約数は1,2,4,7,14,28で1+2+4+7+14=28。同様にして3番目は496、4番目は8128。ここまでは何とか計算できますが5番目は33550336となり、もはや人間の手には負えません。それ以降の完全数はスーパーコンピューターを使って探すことになるのですが、現在のところ51個しか見つかっていません。有限なのか無限なのか、奇数の完全数が存在するのかしないのかなど、解明されていないことの多い不思議な数です。 ところで、6月28日はパフェの日だそうです。その制定に当たって面白いエピソードがあります。「パフェ」はフランスの料理人が「完全なデザート」をめざしてつくったもので、完全という意味の「parfait」と名づけられました。それにちなんで、日本プロ野球初の完全試合が達成された日をパフェの日と定めたのだそうです。 それの日は6月28日。 なんとも不思議な日に完全試合が行われたものですね…。 気がつきましたか? 6と28は共に完全数なのです! そして…その場所は青森市の合浦公園にある青森市営球場だったのです。 [2023.7.18 坂本 徹] 高校生の頃、スマホどころか携帯電話自体が世の中に登場する前で、学校の緊急事項は電話連絡網で伝わっていました。 夏休みのある日、級友のお父様が亡くなったとの連絡が!その友人は部活も一緒でかなり親しい間柄です。 「行かねば!」他の親しい友人と連絡を取り合い、連れ立ってご自宅へお悔やみに行くことにしました。 私の学校は東京を中心に近郊4県から通学してくる私立高校で、私は千葉県、当の彼女は埼玉県。正装でないと…と暑い中わざわざ制服を着て(夏でもジャンパースカートでした)電車に乗ること1時間以上、何と声がけしたら良いかと悲痛な面持ちで話し合いながら家に着きました。 ところが…全然お葬式の雰囲気でない。 勇気を出してベルを鳴らし、出て着たお母様とは全く話が噛み合いません。 そのうち状況を察して「とにかくお上がりなさい」と優しく招き入れてくださったリビングで、亡くなったはずのお父様は白シャツ姿でビールを片手に甲子園を観戦中! ??? 連絡網のどこで情報がすり変わった? 私が訪ねた友人と不幸があった同級生の名前はどちらも〇〇村さん。夏休み明けに伝わった連絡網の内容を順に追って行くと、そう言えば祖母が電話に出たという子がおり、どうやらその辺から人名が変わってしまったようです。 あとで笑い話になった伝言ゲームのような話ですが、私たちの日常もこれとそう変わらないということを、私は肝に命じております。気持ちも内容も正確に伝わる様に、言葉を尽くして、時には反復して、確認までして話しているのに「そういうつもりじゃなかった」ということって意外とありませんか。 人は人の話を聞く時に、知識や経験や五感を働かせて一生懸命理解しようとします。理解しようとするからこそ、フィルターが入ってしまいます。難しい内容であればあるほど、フィルターはたくさん必要になってきます。理解するための基礎知識=フィルターです。さらに聞いた内容を人に伝える時には、それを咀嚼して改めて自分の言葉に置き換えて伝える。人のやり取りは全てが伝言ゲームみたいなものとつくづく感じるこの頃です。 本当は子供のように素直な心で真っ白な頭で、見たり聞いたりすれば良いものをと、自戒の念を込めて思うのですけれどね。 [2023.6 Y.Ohtaka] 大学生のとき、私は山城組という組織に所属していました。ヤクザみたいな名前ですが、現在もマルチパフォーマンス・コミュニティ芸能山城組として活躍している芸能集団です。前身の「ハトの会コーラス」の発足が1968年ですから50年以上の歴史を持ち、全16タイトルに及ぶLP・CD等のリリース、ケチャ祭りの開催、映画AKIRAの音楽担当など、様々な活動を続けています。 その音楽性や芸術性については別の機会に譲ることとして、今回は山城組の組織や仕組みについてのお話をしたいと思います。 ①学生による主体的な運営 運営は大学生のリーダーたちに委ねられていました。公演を行う際の会場の確保やPAシステムの手配、ポスターやチケットの作成など、すべてを学生たちがやるのです。当時は「大学生って凄いなあ」と思うのみでしたが、今思うと、大学生だから凄いのではなく山城組だから凄かったわけで、その背景に山城祥二氏という優れた指導者がいらっしゃったからに他なりません。 ②独特な組織体系 山城組には都内を中心に10数大学から200人以上のメンバーが集まっていました。各大学にそれぞれ「組」と呼ばれるサークルがあって、その集合体が山城組であり「総組」と呼ばれていました。全体練習は週2回、お茶の水女子大学で行われましたが、それ以外の活動は各大学で行われていました。大所帯を円滑に運営するために、地方分権のような仕組みが導入されていたのです。小さな活力を集めて大きな活力を生み出す…凄い仕組みです。 ③プロジェクト制 通常の活動は合唱団としてのものでしたが、それに囚われることなく、山城組は色々なことに挑戦しました。和太鼓だったり、前衛舞踊だったり、シンセサイザーの制作だったり。その都度「プロジェクト」が編成され、言い出しっぺがチーフになるというのが山城流でした。その時は特に気にも留めませんでしたが、よく考えてみると「個々の発想を拾い上げ、誰もがリーダーとなりうる優れた仕組み」だったと思います。 そのプロジェクトのひとつがレコーディングです。ビクターレコードから声がかかり、「恐山」「地の響き」「 やまと幻唱」と一気に3枚のLPを出しました。中でも恐山は、バックバンドが井上堯之、大野克夫(沢田研二のバック、太陽にほえろ、名探偵コナンなどでおなじみ)といった豪華なメンバーでした。実に貴重な経験でした。 もうひとつ、山城組の面白い仕組みを紹介しましょう。「兄弟分」と呼ばれる繋がりです。私の兄貴分はIさん、姉貴分はHさんでした。発声や音取りなどの活動に関わることばかりではなく、大学での勉強方法、健康面や人間関係などに至るまで親身に相談にのってくれました。後に私にもMさんという弟分、Oさんという妹分ができることになりますが、地方から上京したばかりだった私にとって本当にありがたい存在でした。 レスタやキャリサポ、チャレンジチームをはじめ、大学での授業や社会教育の講座など、私の活動の重要な骨格の一部はここがルーツです。50年近く前の記憶ですので正確ではないかもしれません。また、現在の山城組がどういう仕組みで動いているのかはわかりません。しかし、坂本徹の源流のひとつであることに間違いありません。 大きな示唆を与えてくれたことに感謝し、山城組の益々の活躍をお祈りしたいと思います。 [2023.5.18 坂本 徹] 春ですね。桜が満開です。 青森の冬は、白鳥が連れてきて白鳥が連れ去ると、私は勝手に思っています。白鳥って編隊を組んで渡る時すごく大きな声で号令をかけながら飛びます。 秋の夕暮れ、姿は見えなくても空のどこかから白鳥の鳴き声が聞こえてくると「ああ、間もなく冬が来るんだな」と、何とも言えない風情を感じます。一方、冬の終わりの白鳥の声は、もっと空高いところから聞こえて来ます。「もう春がそこまで来ている。冬までさようなら」と言っているようで、秋とは違い何となくワクワクします。 私は県外から来た人間で、季節の移り変わりなど寒いか暑いかくらいでしか感じられない土地に居たので、青森に来た頃花の咲き方にとても感動したのを覚えています。 長い冬をじっと我慢していたかのように、スイセン、桜、チューリップ、ツツジ、あじさいが重なり合うように次々と咲く様子は見事としか言いようがありませんでした。同時期に咲いているようで、ちゃんと咲く順番を守っている。物言わぬ花に、生命の力を強く感じた瞬間でした。 そんな素敵な青森に来てもう30年になろうとしています。津軽弁のヒアリングとリスニングはいまだ上達しませんが、気持ちはすっかり“青森の人”。この地で、この地域の人々と少しでも明るく楽しく生きていければいいなぁと思いながら、日々の活動をしております。 [2023.4 Y.Ohtaka] 昨年9月のブログで紹介した秘密基地が壊れました。屋根に積もった雪の重みで軒先が折れてしまったのです。油断したせいもありますが、今年の雪はそれくらいヘビーだったということでしょう。「大変」だねって? いいえ「楽しい」ですよ。修理もDIYの楽しみですから。 ワープロに一斉変換という機能がありますが、これを日常生活で行ったらどうでしょうか。例えば雪のこと。 「よく降るね」「雪かきでヘトヘト」「これ以上降らないでほしい」などなど、青森の冬場の会話は雪のことばかりです。そして、決まり文句は「大変」です。確かにその通りではあるのですが、この「大変」を「楽しい」に一斉変換してしまうのです。私はこの冬からやってみました。 雪かきは大変⇒雪かきは楽しい 寒いのは大変⇒寒いのは楽しい 青森の冬は大変⇒青森の冬は楽しい 南国の人は雪の大変さを知りません。そのかわり、雪が融け、春の息吹を実感したときの感動的な喜びも知りません。雪かきだって雪国ならではの貴重な体験と思えば「大変」ではなく「楽しい」と感じてきます。寒いからこそ、暖かい部屋でキンキンに冷えたビール🍺を楽しめます。 仕事だってそうです。やることが多くて「大変」ではなくて、やれることが色々あって「楽しい」と変換すれば、チカラがみなぎってきます。 [2023.3.5 坂本 徹] 最近読んだ仏教の本で「全ての執着を捨てることができたら人は幸せになれる」とありました。おお、成程! 執着には1、欲(五欲)への執着 2、見解への執着 3、儀式 儀礼への執着 4、我論への執着の4種類があり、後へいくほど深くなると説いています。(「執着の捨て方」アルボムッレ・スマサラーナ著より) ストレスは「嫌だ」という感情の表れで、自分が正しくて他者が間違っていると感じた時ストレスは大きくなります。たとえ他者の方が理にかなっていなくても、これを許せない己の気持ちが「執着」なのです。要は捨て置きなさいということです。これはアドラーの“課題の分離”に通じるものがあります。 その実践方法として興味深かったのが、物事に感情を付けて見ないという事です。確かに私たちは「(相手が)きっとこう思ってやったんだ」と無意識に想像して、勝手に腹を立てている事って多いですよね。 ある時期私は、密かにチャレンジゲームをしていたことがあります。何かと言うと、運転中急に飛び出して来る車、交通ルールを守らない車など危ない行為をした車にはついムカッとしてしまうものですが、その車を人が運転していると思わないことにしたのです。すると、ただの機械だと思うと「性能が悪いなぁ、仕方ないなぁ」くらいにしか感じなくなるのが自分でも面白くて、しばらく続けていました。何より心穏やかに居られるし。 ですが「嫌だと思う感情は執着から来るのです。執着を捨てなさい」などと言われると、わざわざ車を機械に置き換えて気を休めていたなんて、なんと稚拙な!と悟ったわけです。 言われたこと、やられたこと、起きたこと、全てをただの事象として見るって、簡単なようですごい修練が要ります。ただ、それができるようになれば、心が波立たない“大きな人”になれるだろうなぁ。そして何より自分がとても幸せになれるんだろうなぁ。 [2023.2.10 Y.Ohtaka] 学生団体レスタが、内閣府の主催する「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」の内閣総理大臣賞をいただきました。設立10周年という節目の年にこのような賞をいただき、顧問としては大変嬉しく思うのですが、当の本人たちは「えっ!どうして私たちが?」というのが実感のようです。 確かに、レスタの活動は決して華々しいものではありません。子どもたちと一緒に勉強したり、料理をしたり、絵本を作ったり、工作をしたり、雪遊びをしたり…ごく日常的でありふれたものです。ですから、自分たちでは「たいしたこと」をやっているという意識はないようです。 しかし、彼らはレスタの根幹をよく理解し、「異年齢交流を通して互いに成長する」という目的を見失わずに活動しています。私流にいえば「昭和の空地」、彼ら流に言えば「ドラえもんの空地」が持っていた教育力を現代に蘇らせる…それがレスタの使命だということをよくわかっています。大きな使命ですが彼らに気負いはありません。自分たちも楽しみながら子どもたちと向き合っています。それを10年間続けてきたということで、それ以上でもそれ以下でもありません。 気負わないこと…それが良いのかもしれません。大人の活動は力が入りすぎますが、高校生や大学生という若者たちはそれを自然体でやってしまいます。子どもたちの大好きな食べ物の中にしっかり栄養を加えてある…それがレスタの真骨頂なのでしょう。 ご尽力いただきました、青森市教育委員会、青森県青少年・男女共同参画課、内閣府の皆様に心から感謝申し上げます。コロナのために思うように活動できなかった2年間を乗り越えて、新拠点「れたすハウス」の開設、企画の再開、寺子屋の定期化、ワールドカフェのリアル開催など、2022年はレスタにとって復活の年でもありました。今回の受賞を励みとしながらも、これからも気負わずに楽しみながら、社会にとって大切な活動を続けていってくれるものと思います。 [2022.1.20 坂本 徹] ※写真は百人一首かるたに興ずるレスタメンバー。子どもたちとの前に自分たちがやってみるのがレスタ流です。 今年も残すところあと半月となってしまいました。話題となった大河ドラマも残り1話、まもなくクリスマスそしてすぐお正月です。 昨年から、NPOでクリスマスの時期に「ギビング・ツリー」を行なっています。 もとは、大きなツリーにサンタさんの来ないお子さんが欲しいものを書いて吊るし、道ゆく大人がそれを見て贈りたいプレゼントをそっと木の根元に置くという、心温まるアメリカの習慣だそうです。いもとようこさんの絵本『プレゼントの木』をベースに八戸のこどもはっちさんが2020年に始めたのを参考に、青森市そして今年は弘前市にもエリアを広げて行いました。 色々ツッコミどころの多いギビングツリーではあります。「本当に困っているお子さんなの?」とか「物が指定されてるの?家にあるおもちゃじゃだめなの?」というご意見もあります。でも私たちは福祉団体ではないし、単純に「贈ってあげたい」という気持ち、「誰か分からないけど本当にプレゼントをくれた!」という嬉しい気持ちが大事だと思っています。きっと双方ともに何かが残るはずだと。 嬉しいのは、プレゼントを買って持ってきてくださる時に「私も楽しませてもらいました」と仰ってくださるプレゼンターさんが何人もいらっしゃることです。 そして私たちは、短くてもメッセージを添えて頂くようお願いしています。これが子供達にとってはプレゼント以上に嬉しいようで、クリスマスに受け取りに来てメッセージを見つけた時のお子さんの反応を、プレゼンターの皆さんに是非見せてあげたいと思うのです。 子供達からのお礼メッセージもお届けしていますが、とても可愛らしく、涙して読んだというプレゼンターさんもいらっしゃいました。 もらう幸せは勿論嬉しいです。でもきっと“あげる幸せ”の方が幸福感の持続が長いような気がします。プレゼンターのみなさん、今年もありがとうございます。 メリークリスマス!そして良いお年をお迎えください! [2022.12 Y.O] 小さい頃、私は「缶蹴り」という遊びに夢中になりました。鬼ごっこと隠れんぼを合わせたような遊びで、必要なのは空き缶1個だけ。3人以上いれば男の子でも女の子でも、10人でも20人でも遊べるという優れモノ。来る日も来る日もこの遊びに明け暮れたものです。 基本ルールがシンプルなので、毎日飽きずに遊ぶにはバリエーションの工夫が必要でした。みんなで知恵を出し合って考えたものです。思いついた新しいやり方をルールにするためには話し合いが必要で、あまり仲の良くない子や新入りの子とも話す必要があり、自然に交流が生まれました。 現代のネットゲームは確かに楽しいですが、子どもたちに何を与えてくれるでしょうか。遊びは大人の娯楽とは似て非なるもの。子どもが成長するためのトレーニングの場であるはずです。今の子供たちは、遊んでいるのではなく、遊ばされている…そんな気がしてなりません。 昔遊びは良かったというノスタルジーではありません。創造力が無いとか協調性に欠けるとか言う前に、現代の「空き缶」は何なのかを考えなければなりません。それが、子どもたちから成長の環境を奪った私たち大人の責務だと思うのです。 [2022.11.1 坂本 徹] 2021年6月のブログで私は、ランニングを始めたと宣言しています。体力的に自信のついた私は、自信過剰にも「山で置き去りにされても動揺しないかも」などと調子に乗っています。 それから早1年3ヶ月、明日“アップルマラソン”に出場します。いや10キロですが。2年前の自分には想像だにできなかった事です。 マラソン大会も、コロナの影響で各地で中止になっていました。コロナ禍も年数を重ねると、うまく付き合っていかないとと思う人が増えたのか、もう慣れて危機感が薄まってきたのか、“敵”の性質を理解できてきたのは大きな理由でしょう、イベントや祭りの復活とともに、各地で再開されるようになりました。むしろマラソン大会の復活は、各種イベントの先駆けだったようにも思います。 3年ぶりに青森市で開催された“さくらマラソン”が、私の大会デビューでした。10キロですが。 マラソンの諸先輩方は「普段5キロ走っていれば10キロはいける」と口を揃えて言います。いやいや、物理的に考えてありえないでしょと反発しつつも、歩いたって棄権したって誰にも迷惑かけないし咎められることもないしと思い直し、エントリーしました。 走ってみると、普段と違い車道を堂々と走れることと、名前も知らない沿道の人々や給水所スタッフの方々の応援が驚くほどの力になることに気がつきました。テンションは上がりまくり、勢いで走れてしまいました。ゴールしてからもなお「あと10キロいけるかも」などと大それたことを言ったくらいです。 大人になると応援されることも少なくなってきて、どんな感情が湧いてくるかなんて頭で考えられることしか浮かんでこなかったけれど、こんなに大きな力になるんだと実感できたのでした。 わずか大会2回目の出場で、それも走る前に宣言するのも何ですが、5年以内にフルマラソンに出ます。 [2022.10 Y.Ohtaka] |
アーカイブ
6月 2024
|