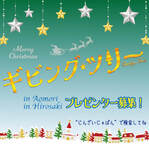|
今年は夏が来るのが早い!青森6月の日中平均気温が26〜28度って、異常です。 そんな暑い(と思われる)夏の終わりに、NPOの新事業として新郷村でアドベンチャーキャンプをやります。なんで新郷?なんでキャンプ?と思われることでしょう。 新郷村には、学校の先生だった理事長のお父上が、不登校の子どもたち及びその家族の交流の場として、私財を投じて建てたログハウスがあります。当時は素晴らしい取り組みとして新聞にも取り上げられた様です。 長らく放置されていたハウスは、痛むこともなく今も立派に佇んでいます。ひと山を購入して建てたので、周りも手付かずの自然がそのまま残った魅力的な環境です。これを有効利用しない方はない! 9月に予定しているキャンプのために、先日第1回目の整備に向かいました。なにかの小動物が一時的に住んだ痕跡はあるものの、ほとんど汚れもなく、今すぐにでも泊まれそうです。(ただし発電機がないと電気がない!ガスもない!) 道中、仲間がニセアカシアの花を天ぷらにすると美味しいと教えてくれました。どこで手に入れるのかと聞くと「その辺で採って食べる」と。「えっ」と少し引き気味に、それでも絶品だというその味に興味津々です。 新郷の山はハウスの掃除や網戸の張替えだけでなく、下草刈りに、茂り過ぎた枝の伐採など力仕事もたくさん。その中で、動線上ない方がいいよねという場所にニセアカシアの木が!手引きのこぎりで伐採できる程度の太さでしたので伐採することにしました。木には花がたくさん、天ぷら素材の宝庫! いやぁ〜美味しかった!まだ味わったことのない方は是非入手して食してみてください。その辺の採って食べようという気になるくらい美味しい。 以来、道路側に茂っているニセアカシアを見ると、もはや巨大な天ぷらにしか見えなくなりました。 いやニセアカシア天ぷらでなく、キャンプ、楽しみにしていて下さい。 [2024.6 Y.Ohtaka] むっちゃんは中学から高校までの同級生でした。中心で活躍するような華やかな人物ではありませんでしたが、物静かだけれどおとなしいわけでもなく、派手ではないけれど清楚で美しく、頭は良かったなぁ。とにかく性格が良い。分け隔てなく、誰にでも丁寧で誰にでも優しい。大好きでした。 私は特に仲良くしていたわけではないけれど、中高一貫で1学年200人しかいない学校だったので、6年の間には大体全員と友達になります。むっちゃんと話すと、ほんわかします。 とても印象に残っているエピソードがあります。 ある時仲良しグループの一人に「むっちゃんて完璧だよね。顔も可愛いし成績もいい。性格もすっごくいいし、欠点ないよね」と言ったら、即答で「欠点がないのが欠点よ」。 え〜っ!?そんなことってある? 発言した友人も、ごく普通の良い子でした。あまりにびっくりしたのでその場はさらっと流してしまいましたが、今だに鮮明に覚えている。そして人の心の機微に興味を持った今、時々思い出しては考えるのです。この言葉が出た心理はなんだろうかと。 友人と私の関係性から考えて、嫉妬ではないと思う。常々むっちゃんへ抱いていた“うらやましい”という気持ちの表れ?特に嫌いではなかったはず。だって嫌いという感情を抱くほど、彼女(友人)もむっちゃんと接点はなかったから。 人は利害に関係なく、いやむしろ利害に関係ないほど他人を叩きたくなるもののようです。 人は論理的にもなかなかなれないらしい。どんなに論理的合理的思考を心がけていても、結局はとっさの直感(感情)に基づいて行動しているという説が結構出ています。 そう考えると、文化文明はものすごく発達したものの、人間て内面的にはどれほどの進化を遂げてきたのでしょうか、もしかしたら退化していたりして。 ただ、とっさの感情を形作るのは経験値です。簡単な例えで言えば、スイカを食べたら甘くてジューシーだったという経験から、夏の暑い日にスイカを見ると喜んで手が出ます。冷えてないなと分かれば、ちょっと躊躇するかもしれない。 経験からくる学びって世の中で認識されている以上に重要です。同じ経験から、人によって何をどれだけ学び取るかは違いがあります。それでも良いのです。大切なのは、「この事からこういう事が学べます」と押し付けるより、学習者を自然とそういう方向に向ける仕掛けです。 さて今年、Jinzaiでは新たな事業として小学生を対象としたキャンプをやります。どんな内容になるか・・・乞うご期待! [2024.04 Y.Ohtaka] 先日、20年ぶりに長崎原爆資料館を訪ねました。前回は修学旅行の引率で慌ただしい日程でしたが今回はゆっくり。目的は原爆の真実を改めて確認すること。 展示室のある地下2階へカウントダウンの数字をたどって円形スロープをゆっくりと下って行きます。2000、1995、1990 ・・・1950 、そして1945年にタイムスリップ。入口に「長崎を最期の被爆地に」 というメッセージと共に、11時2分で止まったままの壊れた時計が展示してあります。 かつて我が家の居間にもそっくりな時計があったのを思い出しました。父母の結婚記念のゼンマイ仕掛けの柱時計です。幼少期から高校まで僕はその時計の下で過ごしました。両親や妹たちに囲まれ、裕福ではないけれど穏やかで平和な暮らしでした。アニメ「サザエさん」のような昭和の時代のささやかな幸せ。あの頃は気にも留めない存在でしたが、柱時計はどの家でも小さな幸せの象徴であったとように思えるのです。長崎にもそんな平和な暮らしがあったはずでした。1945年8月7日 11時2分、それが一瞬にして消え去りました。 他人事ではないのです。たまたま長崎だったのであって、日本中のどこもが被爆地になる可能性があったのですから。当初、原爆投下の第一候補が京都であったことや、模擬原子爆弾による投下訓練が全国30都市で49回も行われていたことはあまり知られていません。8月7日当日も、小倉(北九州市)の予定が天候のせいで急遽長崎に変更されたのでした。 戦争を終わらせるため…今でもそう主張されていますが、だからと言って民間人の大量殺戮が正当化されて良いわけはありません。数々の遺物がその悲惨さを証言し、その後も苦しみ続けた人々の声が聞こえてきます。真実を確認するために再訪したというのに目を覆い耳を塞ぎたくなるほどです。本やネットの情報で理解したつもりになっていましたが、『何も知らなかった自分』に気付かされました。 爆心地に立って辺りを見回すと、そこには静かな公園と住宅街が広がっていました。ゼンマイ仕掛けの柱時計はないかもしれないけれど、どの家でも平和な時が刻まれているはずです。「長崎を最期の被爆地に」 というメッセージと共に。 近いうちに30年ぶりの広島を訪ねようと思います。 [2024.3.26 坂本 徹] 2024年はあらゆることが変わる年と言われています。それは大体占星学や九星気学などいわゆる“占い系”からよく聞こえてくる話ですが、なんだ占いかと侮るなかれ。占いとは、要するに“統計学”です。統計は科学的根拠としてあらゆる論文やプレゼンで使われ信頼度も高いのに、占星などに限って軽く扱われるのはどうしたことでしょう。例えば九星気学などは、天気予報よりも歴史が古いそうです。 未来なんて結局予想がつかないのだから、信用できないといったところでしょうか。 何事もそうですが、要はそれに囚われすぎて行動が偏るのが良くないわけで、雨が降る確率が高いというなら傘を持っていくに越したことはない、その程度にうまく利用すれば良いわけです。 さて2024年は何が変わるかというと、これまでの常識が大きく覆され、是正される年だそうです。 とはいえ、物事ってある日を境に急に変わるものではなく、徐々に徐々に変わる方向に向いていた事や、おかしいんじゃないかと思われながらも潜在していた事柄が明るみに出て正されていくと言った感じでしょうか。世の中のニュースを思い浮かべても、思い当たる事象はありますよね。 何が正しいとは言えない世の中ですが、過去の歴史を顧みると、未熟な人類はこうして過ちを繰り返しながら少しずつ方向修正をして成長していくのかなと思っています。 かくいう私は今年年女。年始のお参りも念入りにしたし・・・と安心していたら、日本の暦では年の変わり目は節分ということを最近知りました。お正月のお参りは年度末のいわばお礼参りにあたり、年始のお参りは2月4日以降ということで、先日岩木山神社に行ってきました。 神社へのお参りも、本来は“お願い”ではなく“宣誓”をする場であり、「私は〇〇をします!」と神様に誓いをたてにいく行為だそうです。だから何度も行って、その度に誓いを思い出し(自己確認し)努力する、目標達成したらお礼参りで報告する。なんて理にかなった先人達の行為でしょうか。神頼みではなく、やっぱり自分次第なのです。 というわけで、岩木山神社でのお参りの内容は・・・内緒です。 [2024.2.6 Y.O.] 明けましておめでとうございます。
昨年は色々とお世話になりました。 チャレンジ先生のエンジョイ講座、ヒューマンライブラリー、高校生チャレンジチーム、ギビングツリー、あおもりゆめ奨学金。 いずれも皆様のご協力とご支援があってのものばかりです。 ありがとうございました。 今年もよろしくお願いいたします。 令和6年が皆様にとって良い年でありますように。 大晦日の紅白歌合戦を珍しくちゃんと見ました。 例年は前半に酔い潰れて気がつくと除夜の鐘だったのですが…。 ゲストで黒柳徹子さんが出演していました。 私にとっての黒柳さんはやはりザ・ベストテンです。 テレビで拝見するのは久しぶりでしたが相変わらず元気いっぱい。 当時と同じ口調の曲紹介を懐かしく思って見ていました。 戦時中は母の郷里である三戸町に疎開していたそうで同い年の90歳。 つい先日、母にねだられて窓際のトットちゃんとその続編を送ったところでした。 それにしてもエネルギッシュな方ですね。 と、ここまで書いたら母からのLINEが届きました。 「明けましておめでとうございます㊗️ 私の希望で、富士山を見に河口湖に向かっています。」 相変わらずアクティブ!!! 長女宅の隣に住んでいるのですが基本的に自炊です。 朝夕2回の散歩を楽しみ、本を読み、絵を描き、ちぎり絵を作る毎日。 月に2回の陶芸教室とその仲間たちとの食事会。 好奇心と食欲は衰えを知りません。 あれが欲しい、これが食べたい、どこそこに行きたい。 頻繁にLINEが届きます。 90歳パワー恐るべし。 令和6年。私も負けないようにアクティブに行こうと思います。 [2024.1.1 坂本 徹] 今年も、私たちにとって12月はギビング・ツリー月間です。 始めてから3年目、事務局としてもだいぶ慣れてきたとはいえ、ハプニングはつきもの。てんやわんやと色々ありつつ、イブの24日に最終日を迎え、子供達にプレゼントをすべて渡し終えました。この日を迎えると「やっぱりやって良かった」と思い、子供達からプレゼンターさんへ送るハガキが届くと、改めて「本当に良かった!世の中捨てたものじゃない!」とつくづく思うのです。 ポジティブ心理学の中で、幸福感を研究するセリグマンはその研究の中で、大変世話になったにもかかわらず感謝の意を伝えていなかった人に感謝の手紙を直接渡すよう支持したグループは、1週間後から1ヶ月後まで長期に幸福感が高かったことを報告しています。またリュボミースキーはさらに、感謝の手紙は相手に届けずただ書くだけでも幸福感が高くなることを報告しています。 人に感謝されたり優しくしてもらうのはもちろん嬉しいことですが、人に感謝したり利他的な行動をとるとより幸福感が高く、長く続くようです。 一方で「〇〇してあげたのにお礼の言葉もない」と怒る人もよく見かけます。気持ちは分かりますが、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。 “〇〇してあげた”きっかけは、相手が「困ってるな」「喜ぶだろうな」と思うから「相手の立場に立ったら、こうしてもらえば嬉しいだろうな」と、自分が思ったからだと思うのです。それだけに何の反応もないと、常識(マナー)に照らし合わせて「何故⁈」という気持ちになるのも当然です。 でもそれは、あくまで自分が「やろう!」と思って“誠意”でやったこと。元々はお礼の言葉や見返りを求めておこした行動ではないはずです。だから、常識的にはちょっと外れるかもしれませんが、ここはひとつ「ま、いいか。あそこでやりたくて行動を起こしたのは自分だし、満足、満足」と思えればもっと平和で素敵ですね。 ギビング・ツリーに宿るのは、そんな精神なんだと思います。何の見返りも求めずにプレゼントを買って贈ってくれるプレゼンターさん達は「楽しかった。参加させてもらってありがとう!」と言って行かれます。 これこそ本来のクリスマスの真骨頂!メリー・クリスマス! [2023.12 Yoriko.O] 平成18年に教育基本法が改正されました。第1条(目的)は、人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという基本的な姿勢を踏襲しています。一方、第2条以降は大幅な変更が加えられました。昭和22年の制定から半世紀以上が経過する中で、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、教育をめぐる状況が大きく変化し、様々な課題が生じていることがその要因と考えられます。 その中で特に注目したいのが第2条(目標)です。これからの苦難の時代を切り開くためとして5項目に渡って教育の具体的な目標が以下のように記されています。 1 幅広い知識と教養 ※ 真理を求める態度 豊かな情操と道徳心 ※ 健やかな身体 ※ 2 個人の価値を尊重 能力,創造性,自主 自律の精神 勤労を重んずる態度 3 正義と責任 男女の平等 自他の敬愛と協力 公共の精神 主体的に社会の形成に参画・発展に寄与 4 生命を尊び 自然を大切に 環境の保全に寄与 5 伝統と文化を尊重 我が国と郷土を愛する 他国を尊重 国際社会の平和 旧基本法の第2条では「実際生活に即す、自発的精神、自他の敬愛と協力、文化の創造と発展」でしたので、ここまで具体的に明示されたのは異例と言えましょう。さらに、平成29年から平成31にかけて学習指導要領も大きな改訂が行われましたが、その前文に教育基本法の第1条(目的)と第2条(目標)がそっくりそのまま記載されています。なぜ、わざわざ貴重な紙面を割いて全文を載せたのか。その意図を考えずにはいられません。 今の日本の教育は、人格の完成を目指し…という教育の目的に本気で取り組んでいると胸を張って言えるでしょうか。中でも、教育の中心たる学校教育において、第2条の目標のどのくらいをカバーできているでしょうか。特に※印以外についてどう取り組めばいいのか…そのことを学校教育は真剣に考えているでしょうか。改正教育基本法や改訂学習指導要領はそのことを厳しく指摘しているように思えてなりません。教育の目的や目標という原点に立ち戻ったとき、 教育の本来の在り方が見えてきます。現状とのギャップを目の当たりにして、私にはやるべきことがまだまだあるように思えます。 今日は青森公立大学の「総合的な学習の時間の指導法」の授業の最終日でした。私の心の叫びが15人の若者に届いたと信じたいものです。 [2023.11.24 坂本 徹] 人の原動力は、気力と体力。 神様は人間をうまく作ったもので、気力・体力は双方バランスを取りながら機能するようです。体力ばかりが突出してうっかりな行動をとってしまったり、気持ちだけが空回りしてうまくいかないことって誰しも経験があるでしょう?一方で、少々疲れ気味なんだけど気力で何とか乗り切った!なんてこともあります。気力と体力は、お互いの多少のマイナスはカバーし合える美しい関係でもあります。 唐突ですがシリーズ化している大和ハウスのCM、クスッと笑いを誘うドラマ仕立てで、悪と戦う“ダイワマン”が主人公です。 このseason2では、新しいダイワマンスーツがお披露目されます。スーツの製作者曰く「このスーツは一切攻撃ができません。そのかわり、戦意を喪失する波動が出るのです」という代物。これって最強じゃないですか!?全ての紛争国に日本から提供したいスーツ。まあ…、このCMが大和ハウスの製品とどう繋がるのかは別として、とても印象に残ったのは事実です。 良いことも悪いことも、“気力”がなければ出来ないんだという当たり前のことを悟ったのがつい先日。病院にも行きましたが、結局風邪だったのかコロナだったのか判然としませんが(因みに罹患から3週間以上たっても周りにコロナ感染者はいないので多分風邪)、熱やだるさはなく、喉の痛みの後、咳と痰と気力喪失という症状でした。 この気力喪失が咳のせいなのか歳のせいなのか、はたまた異常な夏の暑さの後遺症なのか「何もする気がしない」というより「何もかもどうでもいいやっ」という感覚。良いことも悪いことも全てに関心が湧かない、体は動くが心が伴わない、自分がロボットにでもなったよう感じでした。こんなの初めての感覚。こうなると、物事への情熱が消えてしまうと同時に、他人への感情も良いも悪いも消えてしまうということが分かりました。 これがウイルスのせいだとしたら、ウイルス最強。ウイルスで人類滅亡もあり得る?! コロナで精神的に病んだというニュースを多く聞きます。神様の悪戯だとしたら恐ろしい。身体を傷つけるより、こういうことが人を“人”でなくするのかもと、大げさに悟った晩夏の体験でした。 [2023.10. Yoriko.O] 物事には重要なこととそうでもないことがあります。また、急ぐべきこととそうでもないことがあります。この2つの分類を組み合わせると、第1領域時間(重要&緊急)、第2領域時間(重要&非緊急)、第3領域時間(非重要&緊急)、第4領域時間(非重要&非緊急)とういう4つのマトリクスが出来上がります。 普通、真っ先に取り組むのは第1領域時間ですよね。確かに、重要&緊急である第1領域時間に目が行きますが、実はポイントとなるのは重要&非緊急の第2領域時間なのです。自己啓発、日々の学習や練習、長期にわたるプロジェクトの計画や準備、人材育成、メンタルヘルスなどがこれにあたります。 小学生のころ、夏休みの宿題…明日からやろうと思って過ごすうちに、気がついたら明日が始業式。泣きながら宿題をやった経験はありませんか。これは、当初、第2領域時間(重要&非緊急)だったものが、時間の経過によって第1領域時間(重要&緊急)に変化してしまった例です。 重要度は同じも、第1領域時間には余裕がありませんから、「泣きながら」やることになってしまいます。そして、時間に追われますから「やっつけ仕事」になってしまいます。ですから、できたとしても質の低下は否めません。つまり、第1領域時間ではなく第2領域時間のうちに処理すればいいわけですが、ポイントは、そうすることで「第1領域時間にずれ込むことを防止」できるということ所にあります。 重要事項を優先する=第2領域時間を管理する。これはステーブン・R・コヴィーの7つの習慣のおける第3の習慣でもあります。ごく当たり前のことではありますが、意識して臨まないとつい重要なことを先延ばしにしてしまうものです。分かってはいるのですが、僕もまだまだ修行が足りません。今月もブログを書くのが遅くなってしまいました。(反省) [2023.9.27 坂本 徹] 青森市は今、ねぶた祭りの真っ最中。2〜7日の6日間、日中は普通に仕事をしている人々が、どこからこれだけというくらい沢山の人がワサワサと集まってきて、祭りを盛り上げます。3年前囃子方に入り祭りの裏側を見ることができ、支える人の多さに驚きました。 ねぶた本体を作るねぶた師との交流はあまりないので詳しくは分かりませんが、祭りの相当前から多くの人手によって作り上げられていることは、割と知られています。いよいよ本番となると、ねぶたや太鼓台の曳き手、提灯を持つ人、給水リヤカーを引く人、そして囃子方…。台上げ(ねぶたはパーツに分けて作り、本番直前に曳き台に上げながら合体します)作業などは、これらの人が全員で力を合わせて作業をします。 先日「ねぶた囃子、よくやるよね〜。ボランティアだよね〜」と言われました。 やってる本人たちは、ねぶたが好きで好きでたまらず、休暇をとってまで参加するのです。もちろん祭りを盛り上げよう、楽しんでももらおうという気持ちで参加するのですが、誰のためでもなく自分のためにやっているのだと思います。囃子方もこの6日間のために1年中練習をしているわけで、そこに1時間以上かけて通ってくるメンバーもいます。 “祭り馬鹿”といってしまえばそれまでですが、それで楽しんでくれる人が何万人といるわけで、経済効果も考えると社会に十分に影響を与えているのです。 “誰かのために”だけれど、自己犠牲の上に成り立つのではなく、自分も楽しんで行っている。ボランティアって本来そういうものだと思うのです。 ボランティアをされている方のインタビューを見ると「わたしの方がたくさんのものをもらっている」と答える方が多いのもその表れだと思います。 「ボランティアを人手不足の穴埋めと思ってるんじゃないかしら」「交通費ぐらいはもらわないとやってけないよね」などという話を聞くと、とても残念に思います。 ボランティアを頼む側もやる側も、この気持ちを忘れずに取り組めれば、ボランティア活動はもっともっと良い形で発展すると思います。 [2023.08 Y.Ohtaka] |
アーカイブ
6月 2024
|